
file-6 山古志・中山間地の景観再生~新潟県中越地震から3年、再び故郷で暮らすために~
2004年10月23日、震度7の激震に襲われた新潟県中越地方。錦鯉と闘牛、そして「日本の原風景」と賞賛された棚田と集落の家並みで知られる山古志村は壊滅の危機に見舞われました。あれから3年、仮設住宅からようやく人々は戻り始め、ムラづくりが始まろうとしています。しかし、日本の原風景は、今もまだ危機の中。故郷の中山間地を守るための、新たなチャレンジはまだ始まったばかりです。
![]()

土砂崩れ後の改修を終えた土地にはまだ土の色が鮮やかだが、池谷住民が植えたヤマウドは元気に育っていた。収穫できるようになるまではあと2?3年。その頃に山古志はどんな姿になっているか。
長岡市陽光台。住宅街の一角に、山古志の人々が避難生活を送る仮設住宅が立ち並ぶ。ここで暮らす青木幸七さんは“池谷区長”。仮設住宅周囲のささやかなスペースで、昨年採ったウルイの種から苗を育てていた。
ウルイは新潟県内ではよく知られた山菜で、急斜面などに生え、姿は水芭蕉に似ている。青木さんはこれを、工事を終えて土の色が露出したところへ植えられないかと考えている。良い山菜の生える場所の多くは地震による土砂崩れでなくなってしまったと青木さん。
「山古志の生活の基盤は棚田だ。だけど年寄りには田んぼも、畑もきつい。それで山菜だ。これは毎年植えたり、手入れしてやる必要もない。ちょっと出かけて行かれれば採ってこられるから」と青木さんは話す。今年の春には治水工事が完了した、本来ならのり面保護に草の種を植える場所にヤマウドの苗を植えた。これは良いヤマウドの原になると見た青木さんが県の担当者に草の種を植えてくれるなと交渉し、それを面白がった建設業者がヤマウドの苗を寄付。「ここは誰の土地だとかは一切言わない」と決め、陽光台の池谷住民みんなで汗をかいたという。
山古志では最も大きな集落である種苧原は、他の集落と比べると地震の被害は少なかった。ここに住む小川茂さんは、種苧原と池谷をつなぐ国道沿いに、かつての村花であった萩を植えた。「村の花だからね。わざわざ植えないでもある」と小川さん。地震の前から育てていたが、今度は山の斜面にまで増やす計画だ。しかし、「山古志の景観っていう大きなことからすると、こんなのは小ちゃなことでしかないんだよ」と、小川さんは言う。池谷区長の青木さんはかつての土地に家を建築中。まだ山古志に戻れない人は多い。そして3年近い年月の中で戻るのをあきらめた人もまた、少なくはない。山古志の美しい景観は、大自然の美しさではなく暮らす人があってこそのもの。それを取り戻すのは並大抵ではないと、小川さんはみている。
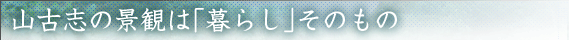
かつて「越(こし)の国」と呼ばれた新潟で、それと同じ音を持った古志(こし)郡山古志村。郡内の他の村が、隣接する小千谷市や長岡市などと合併していく中で、長らく一郡一村を保っていた。標高150?450m程度の山々を縫うように、谷筋ごとに小さな村々が点在し、これらの総称であった山古志が、「山古志村」となったのは昭和31年。当時の人口は9,019人だった。「虫亀」「池谷」「種苧原」などと呼ばれる集落名は、全てかつての村の名である。
土地のほとんどが山か急斜面で、田畑、宅地と池の割合は村の面積の17%しかなく、ほとんどが山林と雑種地。米を作るかたわら縮、炭、山菜などを産業としてきた。山林の多くはムラの共有財産である入会地で、そこで木を伐採して炭を焼き、各家で使う薪を集め、下草は田の肥料として使った。このため山古志では樹木の生い茂った山は少ない。土砂崩れが頻繁に発生する地質で、崩れてなだらかになった土地に棚田を拡げていった。今のように山の上まで棚田があるのは、人口が増えた明治以降といわれている。
この地域で最も古い生活の痕跡は、縄文時代中期から後期。仮設住宅のある陽光台付近で出土した、全国に知られる火焔式土器が作られたのと同じ時代だ。村の記述として残された最も古いものは江戸時代以降で、それ以前のこの地域がどんなであったかはほとんど分かっていない。

水鏡のような棚田が山古志の棚田の、他にはない美しさ。水を確保するための池であり、錦鯉を飼う池でもある。
山古志の棚田の風景を特長づけるのは錦鯉の池である。春から秋まで水をたたえ、小さな鏡の連なりのように陽光を反射する。これが多くの人々を魅了してきた。この錦鯉は、江戸時代後期の大飢饉の際、食用に村で飼われていた鯉を一カ所に集めたところ、その中から突然変異で色のついた鯉が生まれたのが始まりだとされる。天明の飢饉では、山古志全体で341人が餓死。生きるための、村を挙げた懸命の工夫が錦鯉を生み出す契機になった。
そして牛の角突き。江戸時代後期に成立した南総里見八犬伝にこの記述があるが、いつから始まったものかは分かっていない。急な山道が多い山古志では、荷運びや農耕には馬ではなく牛が活躍する。こうした牛はおとなしくするのに去勢するのが一般的だが、山古志ではなぜか去勢せずに飼っていた。山古志村史では角突きの発祥を次のように推測している。去勢しない雄同士が争いを起してけがをしてしまうことがあるため、一堂に集めて角突きをさせ、監視のもとで牛同士に序列をつけさせたのではないかと。牛は闘牛のために飼っているのではなく、ともに働く家族の一員でもあった。このため山古志の角突きは、けがをしたりする前に勝負を止めて勝敗をつけ、その勝負を賭け事の対象にしないのが今も伝統として残っている。

景観にとけ込む外観と自然素材を使用しコストダウンを図った復興住宅。かつては小学校があった丘に、この住宅による小さなコミュニティーができている。
2007年8月、震災後は長岡市の別会場で開いていた闘牛がようやく山古志に戻った。「山古志でなけりゃ闘牛。これでようやく“角突き”になる」と話すのは財団法人山の暮らし再生機構の五十嵐豊さん。生活と文化は切り離すことができないと語る。山古志ではその景観もまた、人々の暮らしから生まれた文化なのだ。その意味で、景観再生は生活再建と切り離すことはできない。
「地震の前からだよ」と言うのは小川茂さんだ。かつては田んぼの肥料にした下草を刈らなくなり、薪炭を求めて山へ入ることもなくなり、地震が起こる前から山は荒れていた。人口減と高齢化で、手間ひまかけて出来上がってきた山古志の棚田と山を守れなくなる日が、いつかはやってくると誰もが想像した。青木さんが山菜を植えるのも「田んぼができなくなった年寄りでも採れるから」という理由だ。1980年から2000年までの20年間の人口減少率は36.7%。そして震災からの3年で25%程度の人口減少になるとみられている。山古志では決してなだらかとは言えない人口減少が、震災によって一気に加速した。
この中でどのように持続可能な暮らしを築いてゆくか。一つは山古志での起業支援、産業起こし、平地と比べて高コストである米の高付加価値化だ。これまでは自家消費だけだった伝統野菜のカグラナンバンの作付けを増やし、地元のスーパーでの取り扱いを始めた。震災後の交流から生まれたコシヒカリ「山古志三人娘」のブランド化、養鯉池を活用した「やまこしモロコ」のブランド化などが同時進行で進められている。中でもやまこしモロコは、新たな特産品づくりと同時に、棚田の景観を保全するという目的もある。親鯉が震災で死に、移入した錦鯉からコイヘルペスが発生。山古志ではほとんどの家が専業ではなく半ば趣味で錦鯉を育てているため、疫病対策を万全にすることに限界がある。錦鯉を育てる家が減ることで水をたたえた棚田も減る。錦鯉の養育で培った技術を生かして新たな特産品を育てることで、棚田の景観を守ろうという取り組みだ。
震災直後、「もう二度と戻れないかも知れない」とつぶやいた住民がいた。全国的には住民が戻るための大規模工事は税金の無駄だという声もあった。多くの支援と引き換えに山古志は「日本にとって必要な場所」であると示さなくてはならない。日本の農業政策、国と地方のあり方は、山古志に有利な方向には進んではいないが、五十嵐さんは「山古志が全国の中山間地のモデルになってゆくようにしたい」と話している。
| 協力:長岡市山古志支所 |
|---|
